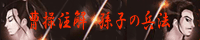☆失敗の法則と原理
☆失敗の法則と原理
成功に法則はない。
しかし、戦略にはタブーがあり、失敗の元凶は厳然たる法則として学習できる。
その証拠が今日のテーマである。
西晋時代に発見された古代春秋時代の竹簡《逸周書・大開武篇》に「七つの失敗の原因(七失)」という教訓がある。
一曰、立在廃(立は廃に在り)
二曰、廃在祇(廃は祇に在り)
三曰、比在門(比は門に在り)
四曰、諂在内(諂は内に在り)
五曰、私在外(私は外に在り)
六曰、私在公(私は公に在り)
七曰、公不違(公は違わず)
その第一は「立在廃」、砂上の楼閣に立つこと。
すなわち、結局は失敗し、烏有に帰する戦略不在のままで、わけもわからずに政策を動かすことである。
これは本講において、戦略のタブーとして、これまで何度も確認した通り。
第二は「廃在祇」、「祇」というのは祭礼のことだが、ここでは思想を意味している。
つまり非建設的で自虐的な思想で物事を考えても幸福にはなれないし、成功はおぼつかない。
昔、《不幸の手紙》というのが流行して、私のところにも何通も届いたことがあった。今風に言えば「手紙ウィルス」で、
「これは不幸の手紙です。同じ文面を五人に送りつけないと、あなたは不幸になります」と脅迫するのである。
私はこんな手紙が来るたびに直ちに焼き捨てた。
呪いや穢れを火で清浄化したのは、私が日本人で知らず知らずに民俗の神道の習慣にしたがったからであるが、これが「祇」にあたる。
正しい信仰があれば精神的な動揺は少なくなる。
信仰がない人間ばかりになると、ありもしない話に動揺し、社会全体が混乱する。
個人的な経験談だが、イタリアのトリノに十字軍がエルサレムから持ち帰った《聖骸布》というキリストの顔と体の姿が転写された布があるというので、私も立ち寄ったことがある。
たまたまトリノ大司教がいたので、
「これは本物なのですか」とラテン語で聞いた。
すると大司教はこう言った。
「この布が本物であっても、私の信仰は変わりません。この布がニセモノであっても、私の信仰は動揺しません」
英語だったら、もちろん無視されたであろう。
私には古い布よりも、老大司教から、この一語を聞いたことがまことに有益だったのである。
幸福や成功とは縁遠い人々が嫉妬や他人の幸福を呪う感情から自虐的で攻撃的な自傷他害の思考方法、マイナス発想を広める。よく考えれば無意味なことで、われわれ自身のやる気や生きがいを見失うこと自体、不幸の始まりだと知るべきである。
第三は「比在門」、「門」というのは権門盛家、つまり有力者である。
有力者たちが権勢を比肩しあい、仲が悪くなり、足の引っ張り合いをやらかすこと。
企業経営でも、中堅リーダーたちのチームワークがうまくいかないと組織はもたない。
内部分裂の根拠をうまく除き去っていけば、設立当初から問題を抱えていた「コクド・西武鉄道グループ」も、あのように隆々たる発展ができるのである。
第四は「諂在内」、「諂」は甘い言葉、へつらい、つまり上の御機嫌をそこねないために、部下が御都合主義で虚偽報告をつくったり、スキャンダルを隠すようになること。
組織の「甘えの構造」でもある。
これは深刻な問題で、以前は警察や外務省、現在は道路公団・社会保険庁が猛烈な社会的な批判を浴びているのも、こうした理由からである。
しかし彼らは
「組織の体面の維持のために必要なことだった」と平然という。
彼らこそ公務員の倫理に反し、法律に違反しているばかりでなく、国家体制の大原則をねじ曲げ、全体の失敗の原因をつくっているのである。
第五は「私在外」、国益や公益、組織の利益などが放擲され、私利によって外部と手を握り、内部を損害にいたらしめる行為である。
これは《キックバック・リベート》の問題で取り上げた。
昔の賢人政治家は、このような利権構造に立場上同調しなければならなかった時、自分では一銭も手をつけず、会社名義の口座をつくって保管し、後に事情をきちんと会社内に説明して経理に入れるようなことをしていた。
『三国志演義』のファンなら、曹操の厚遇に感謝しながら、贈り物はすべて封印して自宅に保管していた関羽のイメージを思い出すだろう。
「私利」を外部から受け取ると、それをもとに、いつ相手が脅迫的な態度に転換し、彼らの利益のために服従を強要するかわからない。
不正な取引をやむをえずに引き取った事情を会社に詳細に説明し、自分に非がないことを明らかにしてあれば、相手が強硬に出てきてたら切り捨てることができる。
それによって会社の損害が大きくなることも阻止できる。
公益と私利の間で進退に迷う人物は人の上に立つ器量ではないが、その一つ先を読んで、このように組織を守りつつ、自分自身も防衛できるような知恵の回る人物でなければ、組織の幹部の器量ではないといえる。
組織の幹部にもならずに、自分だけの生活を楽しもうとするならば、このような先を読む知恵はいらないし、命令されたことを忠実に果たしていればいい。
一念発起して、人の上に立とうと志望したら、部下を過誤に導き、組織を失敗に陥らせるような「私利」は出さないように修養が必要である。
特に心の修養ができていない上司は部下から人間的に尊敬されないから自己顕示の欲求不満になり、ますます道を踏み外してしまいがちになるのである。
第六は「私在公」、「公」は公爵、つまりは王者の側近であり、場合によっては摂政ともなりうる重要な人物。
会社でいえば専務取締役以上の重役を意味する。
これだけの権力の座にある人たちが組織全体の失敗をかえりみずに「私利」をはかることは、やがて大変な結末と損害をもたらすであろう。
ただし、重役という逃げ隠れもできない立場の人々が外からリベートを受け取って脅迫されることはまずありえない。
むしろそこそこの地位にある野心家は、「自分の出世に傷がつく」とか、「部下の失敗に自分まで責任を取らされるのは困る」といった「わが身可愛さ」のゆえにトラブルを起こすのである。
例えば、神奈川県警察本部の本部長は、一警官が愛人と共に覚醒剤を使用して逮捕された事実の隠蔽を指示し、そのために部下に命じて、覚醒剤が検出されたデータを廃棄して、覚醒剤が検出されないような試験をくりかえさせた。
これは彼が主張するような《組織防衛》ではない。
逆に組織の権力を不当に利用して、「こんなことで私に傷がつけられるか。もみ消してしまえ」とばかりに、自分自身の保身をはかろうとしたのである。
その選択がどのような結果になったかは、「身は死に国は滅ぶ」の言葉の通り、彼自身はキャリア警察官僚の地位から刑事被告人に叩き落され、警察組織の改革からスキャンダルの内部告発が頻発し、日本の社会的な混乱は極点に達してしまった。
第七は「公不違」、これはいくつか解釈が可能だが、「公爵が道理に違わない」ということであれば失敗ではなく正鵠であり、問題とはならない。
しかし、「公爵が君主に逆らわず、イエスマンになってしまう」ということであれば、確かに大きな失敗の原因になる。
君主と共に権力の座にある公爵が、君主の人間的な過誤も看過するようでは、小さな過誤でも大きな損害と禍根となるであろう。
例えば、警察本部の本部長が明らかに違法な指示を出していたとき、副本部長が事情を知っていても、「そんなことはやめなさい」と進言できないと、スキャンダル事件発生は誰も止められない。
企業でも、実力のある指導者が万に一つの過ちをしても、取締役がみんなイエスマンだと「失敗の成就」は誰にも止められない。君主の過ちを止めるために、君主に次ぐ高い地位があるのであり、経営指導者の失敗を補うために重役がいるのである。
異論反論を唱える重役を切り捨て、イエスマンだけで重役を固める経営者は、自分がだんだん目が不自由になり、難聴になっていくことを自覚できないで、壁にぶちあたっていくようなものである。
この問題は非常に重大で、古代ローマ共和政においても、平民から選出される護民官(tribunus plebis)の拒否権(veto)は神聖不可侵といわれた。
法人監査役に査察権と拒否権を与えて、企業内の不正を内部で規制するシステムを商法を改正して、はっきりと定義すべきであろう。
以上のように、《逸周書》によれば、物事の失敗の原因は次のように集約されることになる。
(1) 戦略の不在、欠如と失敗
(2) 精神的支柱のない人々の心理的な動揺
(3) 指導者層のチームワークの欠如・内部分裂
(4) 御都合主義と虚偽の隠蔽体質
(5) 不明なリベートの横行による腐敗
(6) 重役が「わが身かわいさ」のためにトラブルの原因をつくること
(7) イエスマン重役ばかりで真理と真相が指導者に見えなくなること
このような《失敗の原因》を見極めて、あらかじめ組織が誤った方向に行かないようにする目利きの感覚が指導者と戦略関係者には必要である。
「このままではいけない」という組織に対する客観的な観察と同時に、現実に応じた問題解決の方策が成功するかどうかをさらに見極める目利きの能力、それが帝王学の重要な一部門である。
指導者の判断に、失敗の原因を見抜くような目利きの力量がないと、部下たちに任せても安心な状態で失敗はしないだろう。
が、トラブルや緊急事態になると、これは通常のやり方は通用しない。
着陸態勢の最悪のタイミングで逆噴射をかけて飛行機を墜落させる心身症のパイロットのように、むしろ指導者と戦略家が組織全体の失墜を招く原因をつくることになるであろう。
戦略そのものの失敗は、《逸周書・宝典篇》に、「謀有十散(策謀には十項目の失敗の原因がある)」と説明されている。
「散」は、戦略目標がはぐらかされて、策謀がダメになるという意味である。
しかし、この本文には欠落があるので、一緒に考えてみよう。
一廃□□□、其行乃泄
二□□□□、□□□□
三浅薄間諜、其謀乃獲
四説叫軽意、乃傷営立
五行恕而不顧、弗憂其図
六極言不度、其謀乃費
七以親為疎、其謀乃虚
八心私慮邊、百事乃避
九愚而自信、不知所守
十不釈太約、見利忘親
最初の一文は「その極秘の行動計画が漏洩する」というものである。
なぜ君主と戦略家しか全体像がわからないはずの戦略計画が漏洩するのか。
私には君主と戦略家の愚かな慢心によるものだと考えられる。
周囲に自慢したい気持ちで、うっかりと口をすべらせてしまうのである。
そこで《孫子兵法》では戦略家の役割を「智名もなく、勇功もなし」と規定し、「真の参謀は無名であれ」と厳しく警告している。
「この参謀はこういう手を使う」という手筋を相手に読まれると、それが失敗の原因になる。
野球でもピッチャーの球威が落ちていないのに、突然連続して打ち込まれたりするのはキャッチャーのサインや手筋が読まれている場合がある。
参謀は戦場で華々しく活躍するわけでもないので、表立って勝利に貢献した功績を認められることもありえない。
戦略家が自分の功績を明らかにしようとしたら、まさに戦略全体を公開しなければならないので、修養ができていないと、思わずそうしてしまうのである。
「話すべき時期が来たら」という理由で、チャーチルやキッシンジャーの回顧録のように公式な手段でリークする場合もあるが、不用意に指導者の一部やスケジュール管理をしている秘書が、敵側に通じた者に情報を渡してしまうと危険である。
話す相手は、功績の争いで無意味な議論をふっかけてくる男性かもしれないし、甘い言葉で近づいてくる誘惑的な女性かもしれない。
企業秘密に関わっている男性社員と社内恋愛をしている女性社員が、実はライバル会社の若手幹部の愛人の一人、つまり女性スパイだったということは実際に起こりうる話である。
与党の国会議員の男性秘書が、野党の女性秘書とひそかに恋愛しているという「噂」が流れて、
「おい、あの秘書は、ついこの前は地方議会の有力者の若い奥さんと一緒に、ハワイで豪勢に遊んだと自慢たらたらしゃべりまくっていたんだぜ」ということになり、
「二人を別れさせろ」とか、
「いやいや、ここまで相手に食い込まれたら、相当に弱みも握られているから、女性秘書の首を切るしかない」と、国政とは関係のないトラブルで野党の組織が大混乱したりする。
そんな経緯をもった男女が「消えたな」と思っていたら、何も事情を知らない別の野党の新人議員のスタッフに採用されたりするから、こうなるとドラキュラ・フランケンシュタイン・ゾンビが一緒に出てくるホラー映画のオンパレードみたいなことになる。
これが「永田町」なのだ。
第二は残念ながら手がかりはない。
原本の竹簡の模本がないからである。
もし、どこかの墳墓に副葬されていても、現代のように保存液で保管しているわけではない。
全く別のテキストが発見されないかぎり復元は無理であろう。
しかし、われわれは「ミロのビーナスの腕」のように、自分からこの問題提起を考え、推理を働かせることはできる。
第三は「スパイのネットワークが手薄なため、スパイが捕らえられて口を割ってしまう」という意味である。
《孫子兵法》にも「五間・五種類のスパイ」という諜報組織が想定され、その組織を引っ張る主役は「反間・二重スパイ」とされている。
敵方のスパイを寝返らせて「二重スパイ」にすれば、敵方の絶大な信頼を得ながら、安全に諜報組織を動かすことができるというのだ。
しかし、この「反間」だけでは組織的な諜報はできない。
したがって、スパイ組織が手薄になると、一人のスパイが危険を冒す回数も必然的に増えてしまい、敵方に不自然な行動を察知される確率も高くなる。
逮捕されると、《孫子兵法》では、
「スパイは自殺して秘密を守ること」となっているが、もちろんスパイだって相当の見返りがないと死ぬ気にもなれない。
だから、逮捕されると、普通の下級スパイは脅かされただけで早々に口を割ってしまうのである。
第四は「指導者が軽い気持ちで、たびたび方針の転換をするものだから、せっかく営々と準備してきたものが役立たなくなり、全体に支障が生じる」ということだ。
これは前講で《孫子兵法》の敦煌残欠本を紹介し、現地現場主義の説明をした通りのことで、ここでも同じ真理が確認される。
第五は「思いやりの温情も度が過ぎてしまうと、組織の規律や待ち合わせ計画のように、秩序を立てて守らなければならない約束がルーズになり、当初の戦略目的が完遂されない」というケースである。
修行もせずに生半可に自立したり、商売に手を出して行き詰まった人々の職業訓練を支援する《愛の貧乏脱出大作戦》というテレビ番組があったが、毎回毎回、愛ゆえの怒号が渦巻くことになった。
時にはキャスターまでが師匠と一緒になって怒声をはりあげるような、本当に始末におえない、だらしない人々、口先だけで自分自身は何もできない人物も登場する。
この番組を見ていてわかることは、中華料理でも、ソバ打ちでも、タコ焼きでも、一流といわれる名店の「巨匠」が最も激怒するのが、訓練を受ける側の「手抜き」である。
それは師匠と一対一の関係では大変な裏切り行為になるのだが、当事者はよくわからず、ボンヤリしていたり、自尊心を否定されて反発したりする。
長くサラリーマン生活をして、脱サラした人はなかなか手抜きの習慣がやめられない。
組織に埋没していた習慣で、師匠が見ていないと思わず手抜きをしてしまう。
悲しいかな、それがサラリーマンをやりつづけながら、会社の誰からも才能や実力を認められることなく、その人柄を信用されることもなく、むしろ有害な存在として否定され、会社組織から体よくお払い箱になった理由でもあるのである。
視聴者にも、それが手にとるようにわかるものだからおそろしい。
そこで師匠が激しく怒号を浴びせ、これまでの自分にとらわれた人々を間違った考え方から脱却させようとするのだが、本人にも「これまでの自分の甘えた生き方、考え方が悪いのだ」という徹底した人生半分の反省が出てこないと挫折して逃げ出すことになる。
温情をかけつづけるのが本当の愛情ではない。
まちがった考え方を正して、手抜きの習慣から脱却しなければ、中華料理はコゲがついても素材に火が通らず、ソバは切り方もそろわず、タコ焼きもグチャグチャになり、それでも平然と店に出して、せっかく来たお客さんを追い返すことになる。
それで客足もなくなって、最悪状態に逆戻り。
こんなことは料理人の世界だけではない。
失業者対策の一つで、職業訓練をする公立専門学校があるが、再就職が難しいといわれる中高年層に最も高い倍率で人気が集まっているのが造園業だという。
しかし造園、庭師の仕事は「庭を持っている人々」が相手の商売であり、庭を持つような高額所得者の実数が増加しないと、造園業で雇用数が増加することはない。
逆に資産家は、親子代々同じ庭の手入れをしてきた庭師の家に仕事を依頼しつづけるのが慣わしだから、相当のコネがないと他人の庭の造作を預かることはできないのだ。
造園といっても庭園の設計は鉢植えの盆栽と違って技術的にも難しい。
排水施設なども必要だし、建物との調和もあるから一級建築士の資格免許がないと独立した仕事は見つからないだろう。
実態を聞いても、造園業を学んで訓練校を卒業をしても、造園関係の仕事に就職できる人は非常に少なく、ほとんどの人々は運送や建設工事などにまわって、職業訓練の成果を生かすチャンスがないという。
すると「人気があり、ニーズがあるから」といって、職業専門学校が造園学科の募集人数を増やしたりしたら、さらに雇用の窓口を狭くして、これは税金を用いて失業者を増加させるだけということになる。
失敗で身もがいている人に冷や水のような批判を浴びせることは人間として心苦しいことは間違いない。
しかし希望者個々人のニーズよりも、社会的なニーズを優先して公立専門校が運営されなければ、結局は就職段階で「雇用のミスマッチ」を拡大することになり、修了者にとっても一年以上のムダを費やして、再び失業状態にもどる不幸を待たせることになる。
売れない商品をテマヒマかけて大量生産しつづけるご苦労な工場に、公権力によって公的資金を投入して操業を続けさせるようなものだ。
このまま現状を放置していたら、血税である公費をかけて熟練労働者の卵を育成する制度そのものが崩壊するのだ。
私は失業者対策も金だけで解決できるとは思えないし、TV番組のような愛と鬼の怒号訓練が、ケース・バイ・ケースには必要になってきていると思う。
また、各企業がほとんど自助努力もしないで、
「政府が景気対策を打てば何とかなるだろう」などという安易な考え方もやめたらいい。
もちろん、そんな時代錯誤のトボケた会社はすでに倒産し、追いつめられた経営者はこの世から消えているだろう。
第六は「言葉だけで大風呂敷を広げる人物の戦略なんかを採用すると膨大な費用がかかる」というので、私などは実に我が意を得たりと思う。
中学生が同じ数学の問題を解くのにも、ポンポンと定理をあてはめて簡単な推論で解答を出す要領のよい生徒がいるかと思えば、やたらに数式をならべてそれでも解答が出ないという要領の悪い生徒もいる。
もちろん、いつも近道がいいというわけではない。
高速道路が渋滞しているときは、一般道の抜け道の方が早いから、「急がば回れ」ということになる。
高速道路と一般道を知りつくしていて、直感的に最良のルートを選んでスイスイ動けば、それも要領がいいわけである。
建物の設計も、利用者のニーズとか、建物の使い道を要領よく把握した設計者が建てると、そんなに維持経費もかからず、使い勝手のよい建物になるが、設計者が金に糸目をつけない公共建築というチャンスに自分勝手な表現を押しつけることで自己顕示欲を織り込もうとしているときには、その維持経費やら補修費用はどんどん膨張していくことであろう。
高層建築のガラス窓一つでも、平面ならば機械のワイパーでも清掃は可能だが、ガラスが曲がっていたり、傾斜していたりすると、人手を使わなくてはならない。
それでも高層建築だから清掃が無理で行き届かないところが出てくると、完成したばかりはすばらしい芸術的な高層窓だったものが、もう数年もたつとひどく薄汚れてしまう。これは設計者が基本デザインの優美さにとらわれすぎ、それを維持するための清掃の利便性を全く考慮に入れていないのである。
《孫子兵法》は「智者の慮は必ず利害を交える」という。物事の決断にあたって利害得失を十分に考慮しなければ、後になって後悔をすることになる。
しかし現地現場主義とはかけ離れ、第一線の人々がどんな苦労を強いられているかを知らない立場の人は後悔どころか、自責の念さえも感じないだろうし、そのために失敗は拡大して、維持経費が余計にかかって税金を無駄にする公共建築が林立することになるのである。
第七は組織の団結と信頼が崩れると、策謀は空虚なものになるという。
古代の王室でいうならば親族の中に仲間はずれ状態の公子がいると、敵国のスパイに目をつけられてそそのかされ、国家機密を漏洩してしまうのである。
外務省の不正経理のように公法に違反することは言語同断であるが、発端となった内部告発は、キャリア幹部と臨時雇員との間に発生した感情的な対立が原因である。
この内部告発は大まかにいえば不正を暴露して悪を正す意味では評価できる。
しかしキャリア官僚が他国に弱みを握られて、外交上に国家に不利益が生じるような形で内部告発が使われると危険である。
それで感情的に対立して、相手を攻撃するような内部告発にならない前に、お互いに失礼がないように批評し、あやまちは正されなくてはならない。
一方で、ライバルの組織が内部に対立をかかえていたら、これを利用しない手はない。
戦国時代末期に秦の宰相・呂不韋という謀略の天才があらわれたが、彼は秦の国益のために働く謀略機関をライバル国の一つ「趙」に置き、金で買収した趙の公子の名前を使って、女性スパイを他国の宮廷に忍び込ませたり、意を受けた腹心を「趙」を経由して、同盟国の政府高官につかせたりした。
女性スパイには必ず兄弟を自称する男性スパイを側近につけ、秘密の恋愛関係を結ばせてコントロールさせるという念の入れぶりであった。
こうした男女が宮廷で子供をつくって権力を握り、各国の政治を大混乱に陥れたのである。
第八は「自分自身の利益ばかりをはかる風潮が蔓延すると、みんなが困難や危険がともなう責任を回避するようになるので、国家は一歩も前進できなくなる」というものである。
アルバイトの学生が自分の失敗の後始末を命じられて、「残業代は出るんですか」といったという昔の笑い話があるが、あちこちで現実にそんな話を耳にしたり、目にすると笑い事ではすまない。
非常な困難や危険がともなう仕事だからこそ、英雄的な努力が賞賛されるのであるが、そうしたヒロイズムを否定しながら、英雄として賞賛されるような貢献もしないくせに、それ以上に自己顕示欲をかかえてしまっている人間は、社長だの医者だのと肩書きを偽ったり、「大きな犯罪でもやって有名になってやろう」という倒錯した方向に走ってしまう。
このような暴虐卑劣な欠陥人間の横暴でも、ある程度まで許容してしまって、ますます図に乗らせて大きな犯罪に走らせているのも、われわれの社会の現実である。
第九は、まさにそんな種類の人間が戦略戦術の実行に関わることを失敗の原因だとする。
「能力もないくせに、自信だけは旺盛だという人物に仕事をまかせたら、他の部門まで大きな被害を出すことになる」というのだ。
このことは日露戦争の203高地の問題で重ねて説明したので、これ以上は述べない。
適材適所ならば成果があがるが、不適当な人材を不適当なポストに置いたりすると、なかなか成果があがらないばかりか、大きな失敗をやらかすことになる。
それでいて、当の本人は「こんな不適当なポストに私を置いたのは誰なのだ」と失敗の原因を人事になすりつけようとする。
人間社会には、いかなる不当な差別もあってはならないが、マーチン・ルーサー・キング牧師の言葉の通り、その人格と識見によって人間は判断されなければならない。
そして国家や組織においては、その人格と識見は成果と利益によって検証されねばならないのである。
さて最後の「不釈太約、見利忘親」だが、戦国時代初期の伝説として、前漢時代の王族・劉向がまとめた《説苑》に次のような残酷なエピソードが引用されている。
「楽羊という魏国の将軍が中山国の都城を攻めて包囲した。ところが楽羊の子はその城で人質になっていた。中山の人々は人質の子を見せしめに城壁に吊るしたが、楽羊はひるむことなく、攻撃を続けた。それで中山の人々は人質の子を煮殺し、使者を送って楽羊に届けさせた。すると楽羊はわが子の煮込み肉を一気に食べ尽くしてしまった。中山の人々は楽羊の意志がこれほどに強固であることを実見し、これ以上の戦いに堪えられなくなって降参を決めた。これによって魏の文侯は初めて自分の領地を拡大することができ、楽羊の功績を表彰したが、その人間性には疑いをもって、それ以降の任用はしなかった。魯の孟孫が狩猟で小鹿をつかまえて、秦西巴という身分の低い者に生け捕り網を取りに行かせた。その小鹿は悲痛にいななき、縄をかけても必死に抵抗した。秦西巴はかわいそうになり、ついに縄をといて逃がしてしまった。孟孫は激怒して秦西巴を免職し、一年以上が過ぎたが、自分の息子の守り役(太傅)を決める時になると、秦西巴を再び呼び出した。あいつは小鹿を逃がした罪で免職になったはずじゃないですかと人々は驚いた。しかし孟孫は、自分の命をかけて小鹿に仁心を示した秦西巴こそ自分の息子を託せる人物だと言って、前例のない抜擢人事をおこなった」
この楽羊のように太約(仁義礼智信)の本質が十分にわかっていないと、自分の子供を煮殺され、戦いに勝っても、自分も子殺しの悪名を着ることになり、君主もまたその誠意と功績は評価しつつも心からの信頼はできないし、外聞をはばかって重任もできないことになる。
大義名分があったから戦争になったのに、領土を拡大しても喜べない。
他に策謀はなかったのかということである。
あるいは楽羊をそこまで追い込んでしまった文侯の人事は正しかったのかということにもなる。
これに対して魯の孟孫は開明な君主であり、今日から見ても「立派な人だ」と思われるであろう。
そのもとになっているのが《太約》、人間社会の不朽の人倫人道の原理なのである。
この時代は、仕事上でミスを犯した者は免職どころか即刻処刑も当たり前であり、世襲の太子の守り役は将来の高官の地位を約束される立場であった。
この人事が当時の社会にどれだけ影響を及ぼしたか。
愛人女性の私生児で、古代社会では身寄りのなかった若い孔子の才能を最初に見出し、首都洛陽に留学させたり、市場の取締役に任用したのも孟孫氏であった。
まさに目利きの天才である。
人間社会における成功や失敗は、古代でも現代でもあまり変わらない。
天地自然の理を私が強調するのも、一時の制度とか、しがらみとかにとらわれて、道理に反する判断に追い込まれ、失敗の渦に巻き込まれることがどんなに恐ろしいことかを痛感してもらいたいのである。
そしてわれわれの目指す戦略学は、このように再現性のある対象をもった普遍的な諸法則の研究体系なのである。
そこで問題。
★あの欠落した第二の部分を、諸君だったらどんな内容だと考えるか。
一廃□□□、其行乃泄
二□□□□、□□□□
三浅薄間諜、其謀乃獲
という本文の流れがあるので、例えば「二□□□□、其○乃○」という定型をふんで意味を考えてもらいたい。
解説したように第一が情報のリーク、第三がスパイ情報ネットワーク整備であるから、われわれが探求している情報戦略の核心における「失敗の原因」が語られていたと思う。
ユニークな解答は無用だ。非実用的な発想も使いものにならない。
どれだけ情報戦略の核心に迫れるか、諸君の真剣な解答を期待したい。